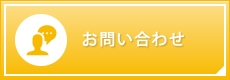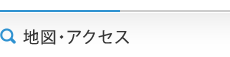相続・遺言の問題
遺言書の作成
遺言とは

民法という法律には,人が亡くなった際に財産を引き継ぐ人(相続人)や,相続人間で財産を配分する割合(法定相続分)が定められていますが,遺言により,遺産を誰にどのように配分するかを原則として自由に決めることができます。
もっとも,遺言書を作成するには,民法が定める方式を守らなければならず,方式に違反している遺言は無効となってしまいます。
また,法定相続人の遺留分を侵害するなど,遺言の内容によっては,後日,相続人間の新たな紛争の種となってしまうこともあります。
遺言書を作成するにあたっては,民法の定める方式を守るとともに,相続人間の紛争の種となることがないよう配慮しつつ,ご自身の意思が実現されるように内容を定めることが必要になります。
遺言の方式
民法は,遺言書の方式として7種類のものを定めていますが,その中でも,自筆証書遺言(民法968条),公正証書遺言(民法969条)を利用するのが一般的です。
【自筆証書遺言】

遺言を残す方が,遺言書の全文,日付,氏名をご自身で手書きし,押印することで作成する遺言書です。
【公正証書遺言】
遺言を残す方が,公証人にどのような遺言を残したいかを話し,公証人がそれを文章にまとめることにより作成される遺言書です。
相続が生じた場合に必要な手続
遺産分割

人が亡くなると,その人の遺産(相続財産)は相続人に引き継がれます(民法896条)。
複数の相続人がいる場合,相続財産は相続人の共有となり(民法898条),相続人は,法律で定められた割合(法定相続分)に従い,相続財産を分配することになります。
この手続を「遺産分割」といいますが,遺産分割の際,相続財産の分配の仕方をめぐって,相続人の間で争いが起きることが少なくありません。
遺産分割は,以下の3つの方法によって行うことができます。
【遺産分割協議】

相続人間の話し合いによって,相続財産の分配の仕方を決める方法です。
協議がまとまった場合には,合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
【遺産分割調停】

相続人間で話し合いがつかない場合などには,家庭裁判所の調停(遺産分割調停)を利用することもできます。
調停では,概ね以下の手順により,調停委員を交えて,合意を目指した話し合いが進められます。
⑴ 相続人の確定
⑵ 遺産の範囲の確定
⑶ 遺産の評価
⑷ 特別受益・寄与分による法定相続分の修正
⑸ 分割方法の決定
【遺産分割審判】

話合いがまとまらず,遺産分割調停が不成立になった場合,自動的に審判手続が開始されます。
審判手続では,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して(民法906条),遺産分割の審判をすることになります。
相続放棄の申述
上記のとおり,人が亡くなると,その人の遺産(相続財産)は相続人に引き継がれますが,このことは,亡くなった方の負債についても当てはまります。
亡くなった方の財産よりも負債が多いなど,相続を希望しない場合,相続人は,原則として相続の開始があったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます(民法955条)。